【歯科医監修】歯周病予防の正しい知識と実践ガイド
歯周病は、日本人成人の約8割が罹患しているとされる非常に身近な病気です。しかし、初期段階では自覚症状が少なく、気づいたときには進行していることも少なくありません。私は歯科医師として多くの患者さんの歯周病治療に携わってきましたが、適切な知識と予防法を知っていれば防げるケースが多いと実感しています。
この記事では、歯周病の基礎知識から予防法、そして最新の治療法まで、歯科医師の視点から詳しく解説します。
歯周病とは?基本的な知識と症状
歯周病とは、歯の周りの歯周組織(歯肉・歯根膜・歯槽骨・セメント質)に炎症が起こっている病気の総称です。初期の段階では歯肉だけに炎症が起こる「歯肉炎」の状態ですが、進行すると歯を支える骨にまで炎症が及ぶ「歯周炎」へと悪化します。
かつては「歯槽膿漏(しそうのうろう)」とも呼ばれていましたが、現在は医学的に「歯周病」という名称が一般的です。
歯周病の主な症状
歯周病の特徴は、初期段階では痛みがほとんどなく静かに進行することです。そのため「サイレント・ディジーズ(静かな病気)」とも呼ばれています。
以下のような症状があれば、歯周病を疑ってみましょう。
- 歯磨き時に歯茎から血が出る
- 歯茎が赤く腫れている
- 口臭が気になる
- 歯茎が下がって歯が長く見える
- 歯がグラグラする
- 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすい
- 朝起きたときに口の中がネバネバする
特に「歯磨きすると血が出る」という症状は、健康な歯茎では起こらないことです。これは歯周病菌と白血球の戦いの証であり、放置すると症状が悪化する可能性があります。
あなたは今、「自分は大丈夫だろう」と思っているかもしれません。しかし、40代では約40%の方が4mm以上の歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)を持っているというデータもあります。
歯周病の進行段階
歯周病は進行度によって以下のように分類されます。
- 健康な状態:薄いピンク色の引き締まった歯茎。出血なし。
- 歯肉炎:歯茎が赤く腫れ、歯磨き時に出血する。適切なケアで回復可能。
- 軽度歯周炎:歯茎の炎症に加え、歯を支える骨がわずかに溶け始める。
- 中等度歯周炎:歯茎が退縮し、歯の根元が露出。歯がやや動揺し始める。
- 重度歯周炎:歯を支える骨が大きく失われ、歯がグラグラする。膿が出ることも。
歯周病は早期発見・早期治療が非常に重要です。歯肉炎の段階であれば、適切なケアによって健康な状態に戻すことができます。しかし、歯周炎に進行すると、失われた骨を元に戻すことは難しくなります。
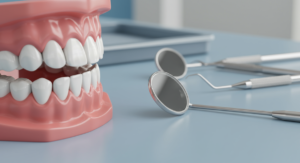
歯周病の原因とリスク要因
歯周病の直接的な原因は「プラーク(歯垢)」です。プラークは歯の表面に付着する細菌の塊で、適切に除去しないと歯茎に炎症を引き起こします。
私の臨床経験でも、日々の歯磨きが不十分な患者さんほど歯周病が進行しているケースが多いです。特に歯と歯茎の境目や歯間部分は、通常の歯磨きだけでは取り除きにくい場所です。
歯周病を引き起こす主な原因
歯周病の主な原因は以下の通りです。
- プラーク(歯垢)の蓄積:細菌の塊であるプラークが歯茎に炎症を引き起こします。
- 歯石:プラークが石灰化して硬くなったもので、表面が粗いため新たなプラークが付着しやすくなります。
- 不適切な歯磨き:歯磨きが不十分だとプラークが残り、逆に強すぎると歯茎を傷つけることがあります。
プラークは、唾液中のタンパク質が歯の表面に付着して薄い膜(ペリクル)を形成し、そこに口腔内の細菌が付着・増殖することで形成されます。歯垢1mgの中には約10億個もの細菌が存在すると言われています。
歯周病の3大リスク因子
歯周病の進行を早める主な危険因子(リスクファクター)として、以下の3つが特に重要です。
- 喫煙:タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯茎の血行不良を引き起こします。また、一酸化炭素により歯周組織が酸素不足になり、歯周病菌に対する抵抗力が低下します。喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病にかかりやすく、治療効果も出にくいことが分かっています。
- 糖尿病:糖尿病患者さんは歯周病になりやすく、また歯周病があると糖尿病も悪化するという相互関係があります。歯周病菌の出す内毒素は血糖値を下げるインスリンの働きを妨げるため、血糖コントロールが難しくなります。
- ストレス:ストレスにより免疫力が低下すると、歯周病菌に対する抵抗力も弱まります。また、ストレスで歯磨きなどの口腔ケアが疎かになることもあります。
私の診療では、禁煙に成功した患者さんの歯周病の症状が改善するケースをよく目にします。喫煙は歯周病の最も大きなリスク因子の一つですので、歯周病予防のためにも禁煙をお勧めします。
また、糖尿病の患者さんには特に丁寧な歯周病ケアが必要です。最近の研究では、徹底した歯周治療によって血糖値が改善されることも分かってきました。
歯周病が全身に及ぼす影響
歯周病は口の中だけの問題ではありません。近年の研究で、歯周病が全身の様々な疾患と関連していることが明らかになってきました。
歯周病菌やその毒素が血流に乗って全身を巡り、様々な臓器に悪影響を及ぼす可能性があるのです。これは「歯科医院に通うことは、単に歯を守るだけでなく、全身の健康を守ることにもつながる」ということを意味しています。
歯周病と関連する全身疾患
歯周病と関連が指摘されている主な全身疾患には以下のようなものがあります。
- 心臓疾患:歯周病菌が血管内に入り込み、動脈硬化を促進する可能性があります。歯周病の人はそうでない人の2.8倍も脳梗塞になりやすいというデータもあります。
- 糖尿病:前述のように、歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼし合います。
- 誤嚥性肺炎:口腔内の細菌が誤って気管に入ることで起こる肺炎で、特に高齢者の死亡原因となることがあります。
- 早産・低体重児出産:妊娠中の歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高める可能性が指摘されています。
- 認知症:最近の研究では、歯周病菌の一種であるP.g菌(Porphyromonas gingivalis)が持つ「ジンジパイン」というタンパク質分解酵素がアルツハイマー病の悪化と関連している可能性が示唆されています。
私が特に注目しているのは、歯周病と認知症の関係です。国立長寿医療研究センターの研究でも、歯周病によって認知機能が低下し、逆に認知機能の低下によって歯周病も悪化するという「歯脳相関」が指摘されています。
歯周病予防は、口腔内の健康だけでなく、全身の健康維持にも重要な役割を果たしています。特に高齢になるほど、その影響は大きくなります。
効果的な歯周病予防法
歯周病予防の基本は「プラークコントロール」です。プラークを効果的に除去し、歯周病菌の増殖を防ぐことが最も重要です。
予防には「セルフケア」と「プロフェッショナルケア」の両方が必要です。どちらか一方だけでは不十分で、両輪として取り組むことが効果的です。
日常的なセルフケア
自宅で毎日行うセルフケアは歯周病予防の基本です。以下のポイントを意識しましょう。
- 正しい歯磨き:歯と歯茎の境目(歯肉溝)を意識して、歯ブラシの毛先を45度の角度で当て、小刻みに動かしましょう。力を入れすぎず、丁寧に磨くことがポイントです。
- 歯間ケア:歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは約60%しか落とせません。デンタルフロスや歯間ブラシを併用しましょう。
- 舌のケア:舌の表面にも細菌は付着します。舌ブラシや歯ブラシの裏側で優しく舌の汚れを取り除きましょう。
- 洗口液の使用:殺菌作用のある洗口液を使用すると、歯ブラシが届きにくい場所の細菌も減らせます。
私がよく患者さんに伝えているのは、「磨く順番を決めておく」ということです。いつも同じ順序で磨くことで、磨き残しが減ります。
また、電動歯ブラシは手磨きよりもプラーク除去効果が高いというデータもあります。特に高齢の方や手先の器用さに自信がない方には、電動歯ブラシをお勧めしています。
プロフェッショナルケア(歯科医院でのケア)
自己流のケアだけでは限界があります。定期的に歯科医院を受診し、プロフェッショナルケアを受けることも重要です。
- 定期検診:半年から1年に1回は歯科検診を受けましょう。歯周病のリスクが高い方は、3〜4ヶ月ごとの受診をお勧めします。
- スケーリング:歯石は自分では除去できないため、歯科医院での専門的なクリーニング(スケーリング)が必要です。
- PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning):歯科衛生士による専門的な歯面清掃です。通常の歯磨きでは落としきれない汚れも除去できます。
- 正しい歯磨き指導:自分に合った歯磨き方法を歯科医師や歯科衛生士から指導してもらいましょう。
私の医院では、患者さん一人ひとりの口腔内状態に合わせたケアプランを提案しています。特に歯周病リスクの高い方には、より頻度の高い定期検診をお勧めしています。
歯科医院での定期的なメンテナンスを受けている患者さんは、そうでない患者さんに比べて歯の喪失リスクが大幅に低下するというデータもあります。
歯周病の最新治療法
歯周病の治療は、症状の進行度に応じて様々な方法があります。基本的な流れとしては、まず歯石除去などの基本治療を行い、必要に応じて外科的治療へと進みます。
近年は技術の進歩により、より効果的で患者さんの負担が少ない治療法も増えてきました。
基本的な歯周病治療
歯周病治療の基本は以下の通りです。
- スケーリング・ルートプレーニング:歯石を除去し、歯の根の表面を滑らかにする処置です。歯肉炎から中等度の歯周炎までの基本的な治療法です。
- 薬物療法:抗菌薬の服用や抗菌成分を含む洗口液の使用により、歯周病菌を減らします。
- 咬合調整:歯に加わる力が強すぎると歯周組織にダメージを与えるため、噛み合わせを調整することもあります。
これらの基本治療で改善しない場合は、外科的治療を検討します。
最新の歯周病治療
歯科医療の進歩により、より効果的な治療法も登場しています。
- レーザー治療:特殊なレーザーを用いて歯周ポケット内の細菌を殺菌し、炎症を抑える治療法です。痛みが少なく、回復も早いのが特徴です。
- 再生療法:失われた歯周組織を再生させる治療法です。エムドゲイン®などの特殊なタンパク質を用いて、骨や歯根膜の再生を促します。
- 歯周組織再生誘導法(GTR法):特殊な膜を用いて、失われた歯槽骨の再生を促す方法です。
- マイクロスコープを用いた精密治療:歯科用顕微鏡を使用することで、肉眼では見えない細部まで確認しながら精密な治療が可能になります。
当院では、患者さんの負担を軽減するために歯科用レーザーを導入し、痛みの少ない治療を心がけています。また、マイクロスコープなどの最新機器を用いた精密治療も行っています。
あなたの症状に最適な治療法は、歯周病の進行度や全身状態によって異なります。まずは歯科医院で詳しい検査を受けることをお勧めします。
まとめ:歯周病予防で健康な歯を守ろう
歯周病は早期発見・早期治療が何よりも重要です。初期段階であれば、適切なケアによって健康な状態に戻すことができます。
歯周病予防の基本は以下の3点です。
- 毎日の正しい歯磨きと歯間ケア
- 定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア
- 喫煙、糖尿病、ストレスなどのリスク因子の管理
また、歯周病は全身の健康とも密接に関連しています。口腔内の健康を守ることは、心臓病や糖尿病、認知症などの予防にもつながります。
「歯磨きをしても血が出る」「口臭が気になる」などの症状がある方は、早めに歯科医院を受診することをお勧めします。
私たち赤坂ONO Dental Clinicでは、一人ひとりの患者さんに合わせた歯周病予防・治療プランをご提案しています。カウンセリングを重視し、患者さんの理解と納得を得た上で治療を進めていますので、お気軽にご相談ください。
健康な歯で美味しく食事を楽しみ、笑顔で会話できる生活は、人生の質を大きく左右します。今日からできる歯周病予防で、あなたの大切な歯を守りましょう。
詳しい情報や診療についてのご質問は、赤坂ONO Dental Clinicまでお気軽にお問い合わせください。
監修者プロフィール
院長 小野 雄大(おの たけひろ)先生



